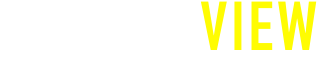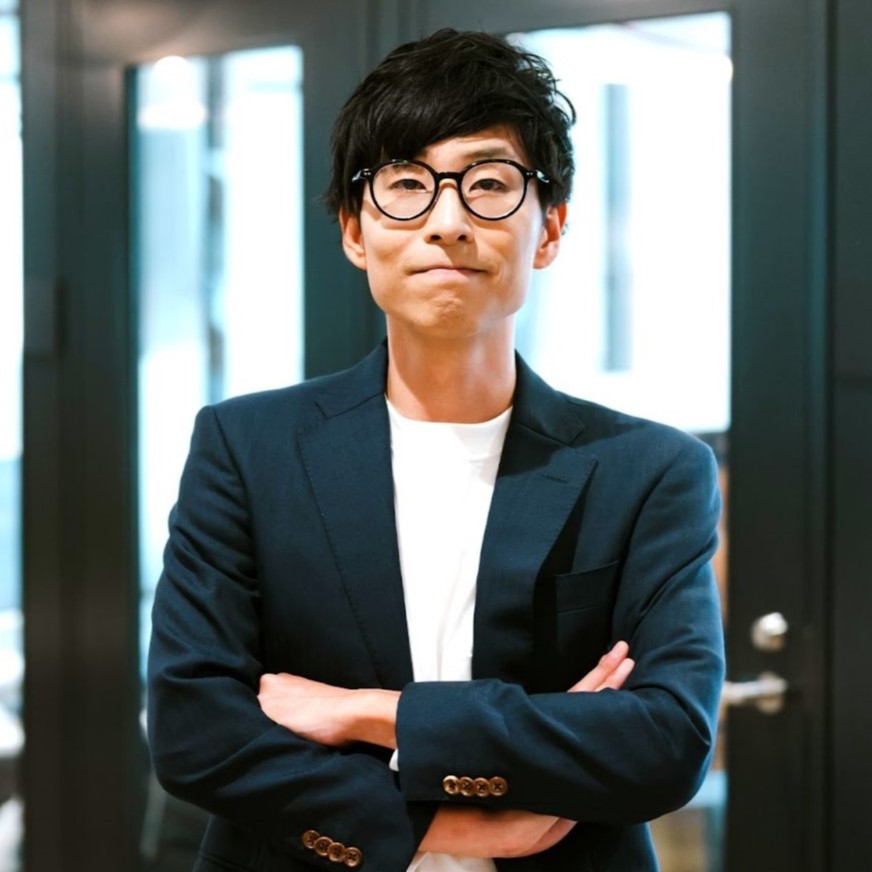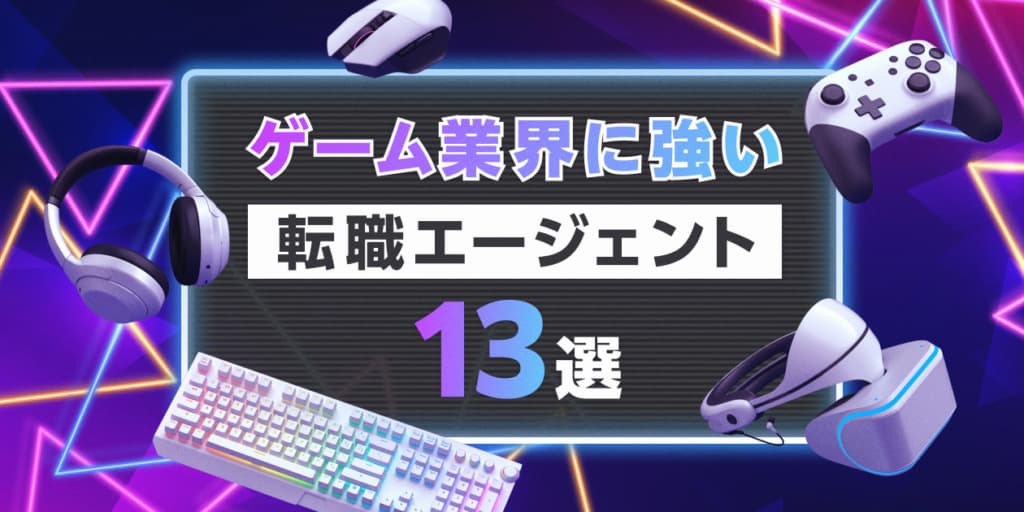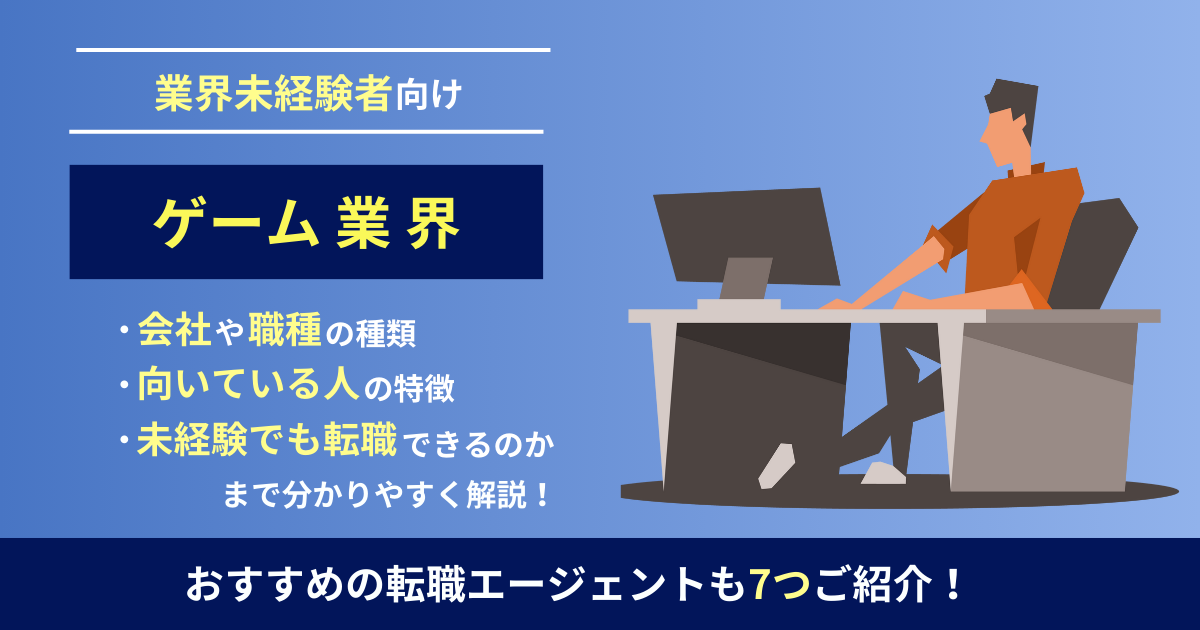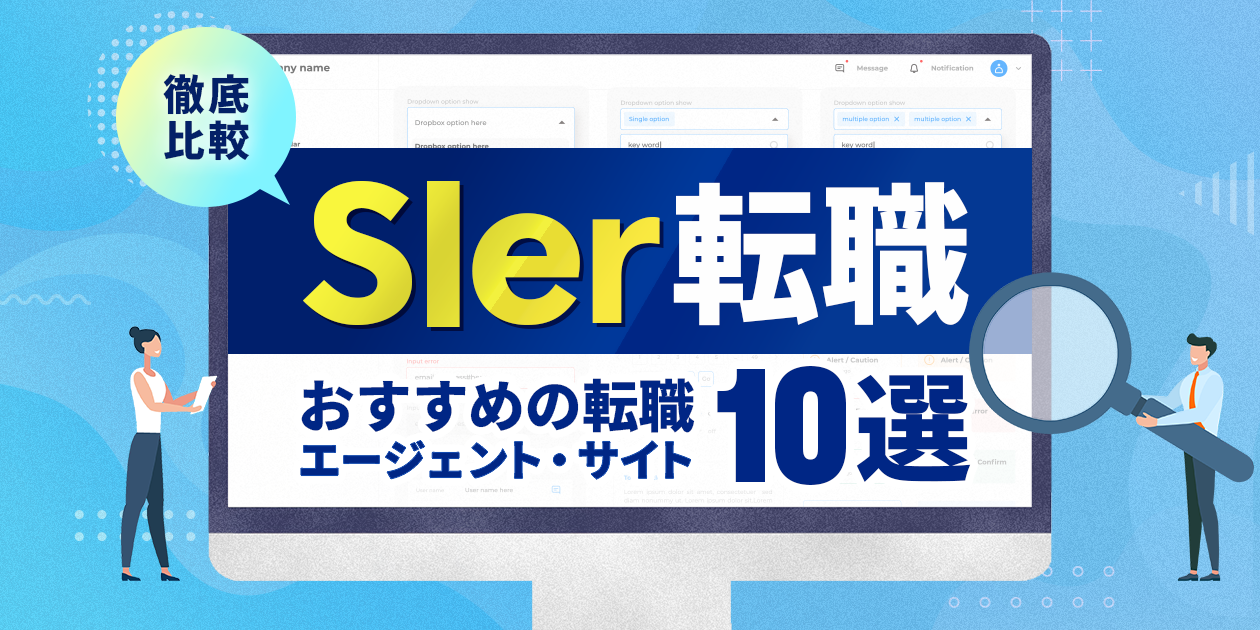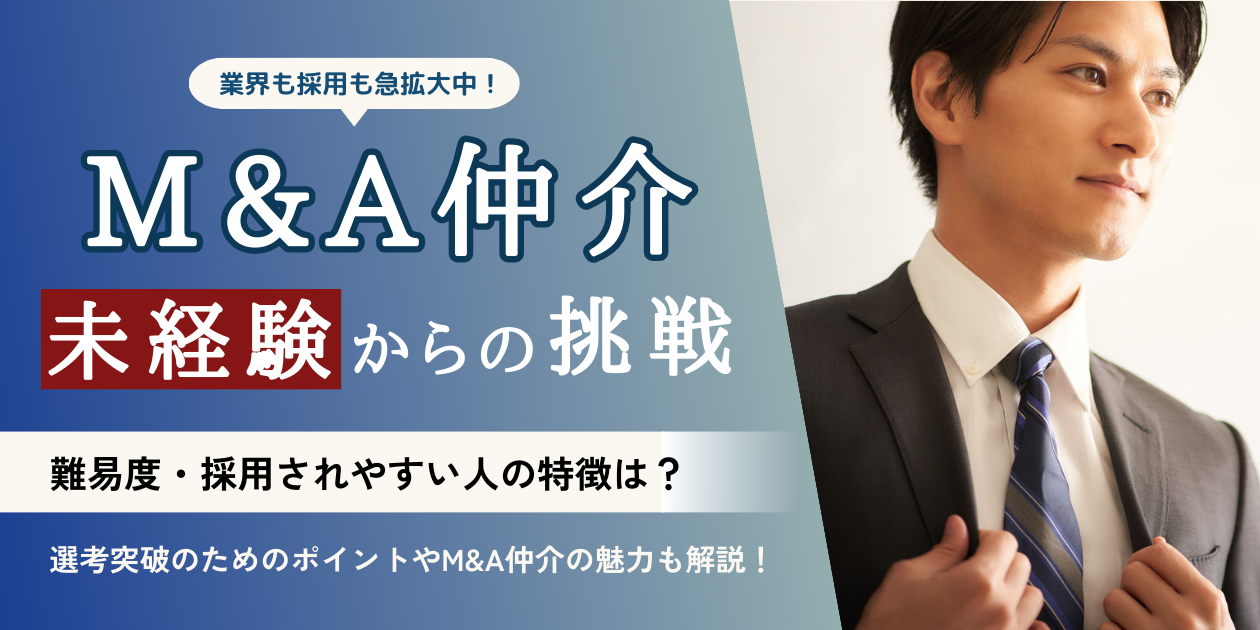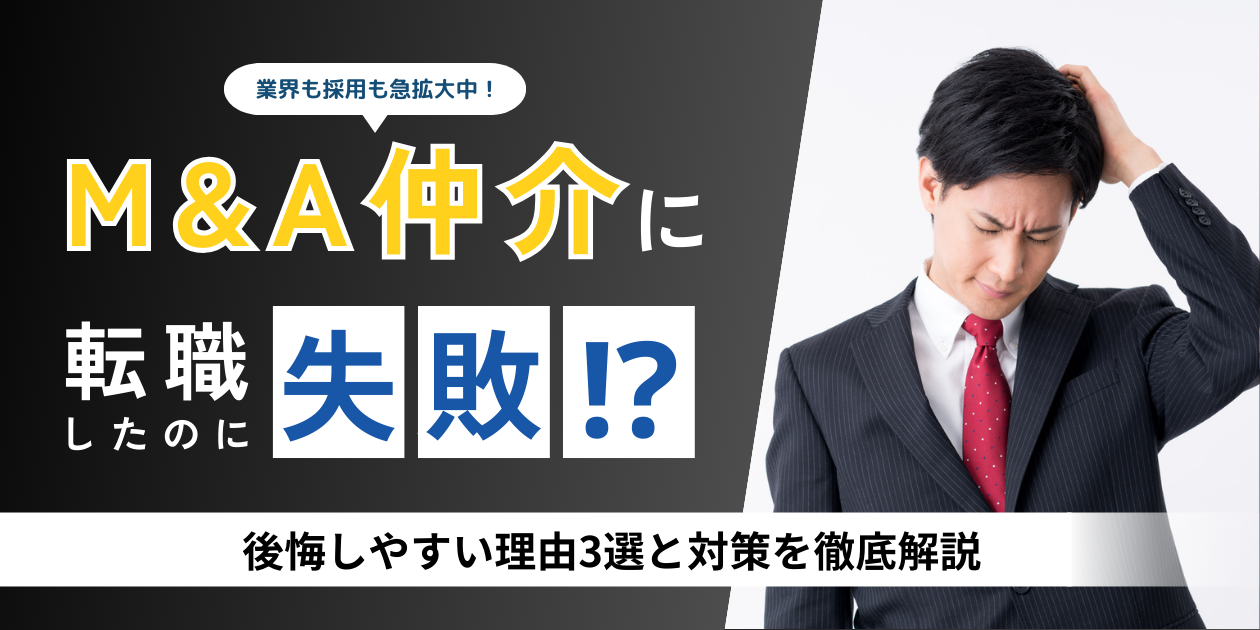ゲーム業界は今後どうなる?今後の動向や10年後の予測などを徹底解説!
近年非常に人気が高いゲーム業界ですが、今後はどのように変化していくのか気になっている方も多いと思います。
本記事では、ゲーム業界の今後のトレンドや動向、10年後の予測やAIによる影響などについて解説していきます。
ゲーム業界への転職を考えている方におすすめの記事
この記事はPRを含みます
目次
【2025年最新版】ゲーム業界の今後の動向と注目トレンド
BCGの調査によると、2019年時点での市場規模が1630億ドルであったゲーム業界は今後も成長を続け、2028年には約1.5倍の2660億ドルにまで達すると予想されています。(参照:BCG「日本のゲーマーは世界と比べ支払い意欲が低い」)
そんなゲーム業界は、今後大きな変革期に入ることが予想されます。ここでは、今後のゲーム業界のトレンドや動向について紹介します。
ゲーム業界の5つのトレンド・動向
- クラウドゲームの市場規模拡大
- eスポーツ市場の拡大
- VR・ARなどのメタバースゲームの市場拡大
- 生成AIを取り込んだゲームの誕生
- サブスクリプション型ゲームの台頭
クラウドゲームの市場規模拡大
クラウドゲームとは、クラウドサーバー上でプレイに必要なデータ処理をすべて簡潔させる形のゲームです。
現状はまだ市場規模も小さく有名ではありませんが、主なものとして以下のようなものがリリースされています。
Facebook:Facebook Gaming
Microsoft:Xbox Cloud Gaming
クラウドゲームは通信環境の影響を受けやすく、アクセス集中による遅延や画質低下・通信環境の質の向上が課題です。しかし、近年の5G・6G通信の普及により、これらの問題が改善されると期待されています。
アプリやソフトのインストールが不要という利便性から、環境が整えば主流プラットフォームとなる可能性を秘めています。
eスポーツ市場の拡大
eスポーツは、ゲーム自体だけでなくスポンサー料、グッズ販売、チケット、配信権などによって大きな経済効果を生み出しています。
eスポーツ市場規模は、2021年時点では国内で約78.4億円、世界で約1,188億円(1ドル=110円換算)でしたが、2024年には世界市場が約1,782億円に拡大する見込みです。
今後さらに認知が広がることで、関連産業を含めた経済効果の拡大が期待されています。
VR・ARなどのメタバースゲームの市場拡大
VR・AR技術を活用したメタバース型ゲームも今後の成長分野です。
総務省の調査では、メタバース×ゲームの世界市場規模は2022年に約102億ドルでしたが、2030年には約1,684億ドルまで拡大すると予測されています。
普及の課題としては、VRデバイスの高価格・通信技術の制約・生活環境への浸透不足が挙げられます。
これらが解決されインフラが整えば、急速な市場拡大が見込まれます。
今後はメタバースとゲームの融合により、新たなゲーム体験やビジネスモデルの誕生が期待されています。
生成AIを取り込んだゲームの誕生
近年注目される生成AIの活用により、ゲーム体験はさらに進化すると考えられます。
従来のゲームではキャラクターのセリフや行動はあらかじめ決められていますが、AIを組み込むことでプレイヤーの行動に応じて会話や展開が変化する可能性があります。
こうした仕組みによって、より没入感のあるパーソナライズドな体験を提供できるようになります。
生成AIの進化は、ゲームデザインやストーリーテリングの在り方を根本から変える要素になるでしょう。
サブスクリプション型ゲームの台頭
サブスクリプション型ゲームとは、月額定額で多数のゲームタイトルを遊べるサービスです。
例として、以下のようなものがあります。
- PlayStation Now:PlayStation3・4の約400タイトルが遊び放題
- Xbox Game Pass:200以上の人気タイトルを提供
定額制により、過去の名作から最新作まで幅広く楽しめる点が魅力です。
このようなサブスク型モデルは、ユーザーの選択肢を広げ、業界全体の市場拡大に貢献しています。
ゲーム業界は10年後どうなる?今後の変化を徹底予測
ここでは、先ほど紹介したゲーム業界の今後の動向やトレンドをもとに、10年後のゲーム業界はどのようになっているのか予測していきます。
ゲーム業界の10年後
- 新たなビジネスモデルにより経済的な流動性が高まる
- ゲーム×リアルの融合で新たなユーザー体験が生まれる
- ゲームと社会が融合している
新たなビジネスモデルにより経済的な流動性が高まる
現在eスポーツやサブスクリプション型ゲームなど、10年前には存在しなかったビジネスモデルが次々と誕生しています。
10年後には、こうしたビジネスモデルがさらに発展し、ユーザー参加型のゲーム経済が一般化すると考えられます。
これにより、プレイヤー一人ひとりが自分に合った体験を選べるようになり、業界全体の経済的流動性が高まることが予想されます。
ゲーム×リアルの融合で新たなユーザー体験が生まれる
次の10年で、ゲームは「画面の中の世界」から「現実とシームレスに繋がる世界」へと進化します。
ARやVR、AIキャラクターなどの技術が進化したことで、プレイヤーの現実行動がそのままゲーム体験に反映される時代が到来すると予想されます。
たとえば、メガネ型デバイスを装着するだけで、街中がクエストフィールドに変化し、AIキャラクターがリアルタイムで会話、現実空間とデジタル空間の区別が曖昧になるような没入型体験が可能になります。
また通信回線・量子コンピューティング技術の発展に伴い、映像表現や動作も現実と差がないほどになると予測されます。
これにより、「体験のリアル化」と「ストーリーの個別最適化」が同時に進行し、プレイヤーの没入感は飛躍的に高まります。
ゲームと社会が融合している
10年後の社会では、ゲームは単なる娯楽ではなく、社会の仕組みの一部として機能している可能性が高いです。
教育・医療・仕事・行政といった領域で、ゲームの仕組みを応用した「ゲーミフィケーション」が標準化されることも期待できます。例えば、教育分野では、AIが学習進度を分析し、ゲーム形式で課題を提示する学習型ゲームシステムが、 医療現場では、患者のリハビリを支援するインタラクティブな治療用ゲームの導入などです。
さらに、eスポーツやメタバース空間での交流が一般化したことで、リアルな社会関係よりもゲーム内コミュニティの方が深いという人々も増加しています。
このように、ゲームはもはや娯楽を超えて教育・交流・経済・文化をつなぐ社会基盤として機能していくでしょう。
ゲーム業界に将来性はある?成長を支える3つの理由
今後も成長していくと考えられているゲーム業界の将来性は、言うまでもなくあるでしょう。
では、その成長を支える軸はどこにあるのでしょうか?考えられるものを3つご紹介します。
ゲーム業界の成長を支える3つの軸
- 新たなユーザーの獲得による市場拡大
- 端末・ハードに依存しない環境整備
- ゲーム×社会による新たな経済効果
新たなユーザーの獲得による市場拡大
今後のゲーム業界では、新たなユーザー層の獲得が成長を支える重要な要素になると考えられます。
その手段として注目されているのが、懐かしの名作ゲームの進化型リメイクと新技術を活用した次世代ゲームの2つの方向性です。
まず、過去に人気を博したタイトルを新たなユーザー体験を盛り込んでリメイクすることで、当時プレイしていたユーザーに再び訴求する効果を期待できます。
また、VR・ARなどのメタバース技術やAIなどの新技術を取り入れた新しい形のゲームは、従来のゲームに興味を示さなかった層の開拓につながります。
このように、「懐かしさで既存ユーザーを呼び戻す流れ」と「最新技術で新規層を開拓する動き」が両輪となることで、ゲーム業界は今後さらに幅広い世代と興味層を巻き込む市場へと進化していくと考えられます。
端末・ハードに依存しない環境整備
現在のゲーム業界では、「ゲームを始めるまでの初期コスト」が大きなハードルの一つとなっています。
コンシューマ機や高性能パソコンを購入するには数万円〜十数万円の費用がかかり、経済的な負担が大きいのが現状です。
この課題を解決するには、端末やハードに依存しないでプレイできる環境の整備が重要です。
たとえば、パソコン向けゲームをコンシューマ機でも遊べるようにする、あるいはコンシューマ向けタイトルをパソコンやスマートフォンでプレイ可能にするなど、クロスプラットフォーム化の推進が挙げられます。
さらに、クラウド技術の発展により、デバイス性能に依存せずゲームをストリーミングで楽しめるクラウドゲーミング環境の整備も進んでいます。
これにより、高価なハードを購入せずとも高品質なゲーム体験が可能となり、価格面で参入をためらっていたユーザー層の獲得につながるでしょう。
ゲーム×社会による新たな経済効果
今後のゲーム業界では、ゲームが個人の娯楽から社会的な価値を持つプラットフォームへと進化していくことで成長が促進されるでしょう。
eスポーツをはじめとするオンライン対戦は、国や地域を越えた経済活動を生み出し、新たな産業構造を形成しています。
また、「ゲーム×行政」「ゲーム×教育」などの分野では、ゲーミフィケーションの導入によって社会課題の解決や地域活性化が進んでいます。
このように、ゲームが社会全体に浸透することで、経済・教育・文化の3つの側面で新たな効果を生み出すことが期待されます。
ゲーム会社の売上高ランキングを確認する
【10年後も価値が落ちない】今後のゲーム業界で市場価値を上げるスキル3選
10年後もゲーム業界で活躍し続けるために今身に着けておきたいスキルをご紹介します。
・AIリテラシー・高度な専門知識
・戦略的に考え行動できるスキル
【発想力】クリエイティブなスキル
今後のゲーム業界で最も価値が落ちにくいのが、創造的な発想力と表現力です。
AIは単純な業務フローを担当するのは得意ですが、「人の感情を動かす体験」や「共感を生む物語」を設計できるのは人間だけです。
AIが生成したアイデアを土台に、「そこから何を感じ取り、どう進化させるか」という人間らしい解釈力が今後の差を生むでしょう。
AIリテラシー・高度な専門知識
次の10年は、「AIを使いこなせる人」と「AIに使われる人」の差がはっきりと出ます。
そのため、ゲーム開発や運営にAIを活用できるAIリテラシーは、すべての職種で不可欠なスキルとなります。
AIを理解するとは、単にツールを使えることではなく、「AIにどのような指示を出せば、理想の結果を得られるのか」を設計・改善できる力、つまりプロンプト設計能力を持つことです。
さらに、AIの挙動や限界を理解するためのプログラミング・データ分析・システム設計の高度な専門知識を有する人も求められるでしょう。
今後AIと組み合わせてゲームが進化していくためには、このような高度な専門知識は必ず求められるスキルといえます。
戦略的に考え行動できるスキル
テクノロジーが発達し、ゲーム開発が複雑化するほど、戦略的に考え行動できるスキルが求められます。
これは、チーム・プロジェクト・市場のすべてを俯瞰し、最適な判断を下す総合的思考力を意味します。
具体的には、以下のようなものです。
・チームをまとめるリーダーシップとコミュニケーション能力
・ユーザー・市場・技術の変化を読んで企画に落とし込むマーケティング視点
また、AIが生み出したデータやアイデアを「どのように戦略へ落とし込むか」という判断力も人間にしかできません。テクノロジーとクリエイティブをつなぐハブのような存在が、今後のゲーム業界で最も重宝される人材となるでしょう。
ゲーム業界に向いている人とは?
ゲーム業界は今後AIでどう変わる?10年後も求められる職種とは
10年間で最も変化するものの一つとして「生成AIとの共存」が挙げられます。この生成AI時代において10年後も残り続ける職種となくなる可能性のある職種を予想していきます。
ゲーム業界で10年後も残り続ける職種
10年後も残り続ける職種を大きくまとめると、「ゲームの開発の中核を担う職種」と「独自の技術や創造性を必要とする職種」の2つになります。詳細な職種は以下にまとめておきます。
ゲームの開発の中核を担う職種
(ゲーム開発 〜 プロモーション・ゲーム販売というプロジェクト全体を統括するマネージャー)
・ゲームプロディーサー
(ゲーム開発工程の責任者)
・ゲームプランナー
(ゲームの企画を作り出す仕事)
・ゲームデザイナー
(ゲームの企画を作り出す仕事)
独自の技術や創造性を必要とする職種
(ゲームの物語を書き、ストーリーを作り上げていく仕事)
・AIエンジニア・ツール開発者
(AI系の技術者)
・サウンドクリエイター
(ゲーム内の音楽の作成をする仕事)
これらの職種はAIによる代替が難しいまたは、人の創造性や感受性を必要とする職種であるため、10年後も残り続けると推測されます。
ゲーム業界で10年後になくなる可能性が高い職種
こちらは、「AIが代わりに行うことができる業務を担当する職種」が当てはまります。主なものとして以下のものが当てはまる可能性があります。
10年後になくなっている可能性のある職種
・デバッカー/テスター
・3Dモデラ―
・データアナリスト
なくなる可能性があると記載しましたが、なくなるのは単純作業を担う業務フローが主なものになると予測されます。
そのため、高度な技術を有している方やAIとの掛け合わせによる生産性向上の実現ができている方は、これらの職種でも活躍の場がある可能性はあるでしょう。
ゲーム業界はやめとくべき?
【まとめ】10年後を見据えてゲーム業界でキャリアを築こう
ゲーム業界は、今後も成長を続け将来性も十分にある業界といえます。しかし一方で、大きな変革期に入っていることもまた事実です。そんなゲーム業界で今後も活躍していくためには、10年後も見据えたキャリアについて考える必要があります。
転職エージェントでは、キャリア形成のための相談という形での利用方法もあります。転職に迷っている方、一度キャリアについて見つめなおしたい方はぜひ相談から利用してみてください。
ゲーム業界の転職エージェントを比較する
ゲーム業界専門のおすすめ転職エージェント3選【無料で活用可能】
- ゲーム業界専門の転職エージェント
- 必ず経験・知識豊富なコンサルタントにサポートしてもらえる
- 内定まで最短3日といったスピード実績あり
- フリーランス・リモート案件も多数