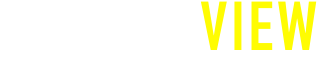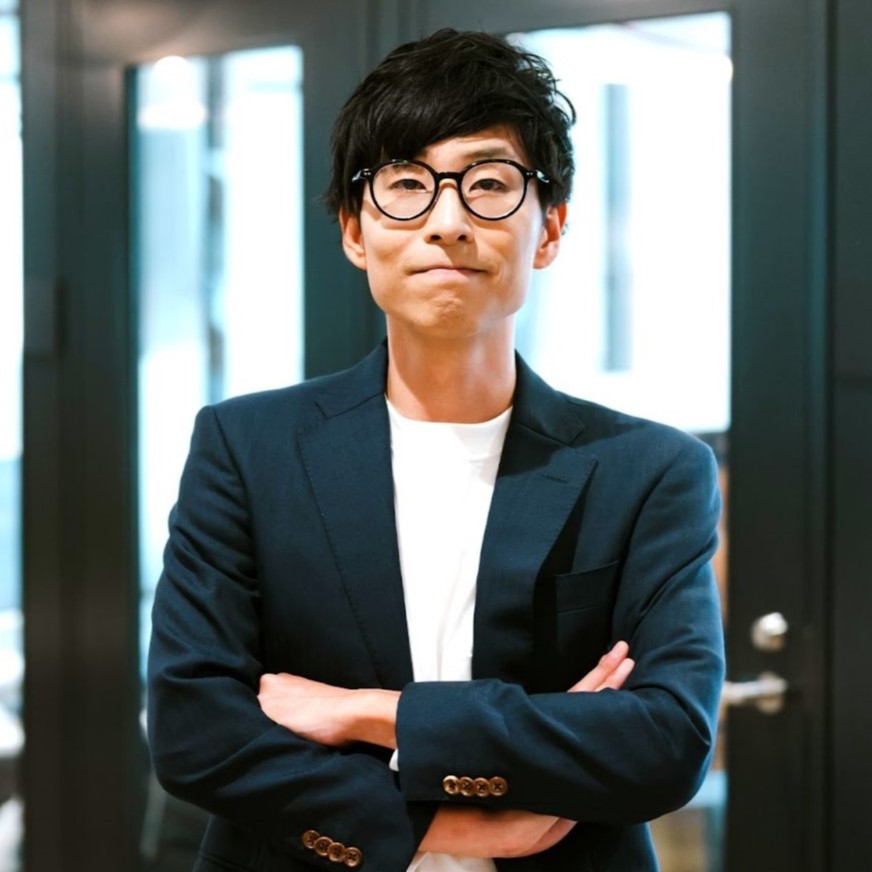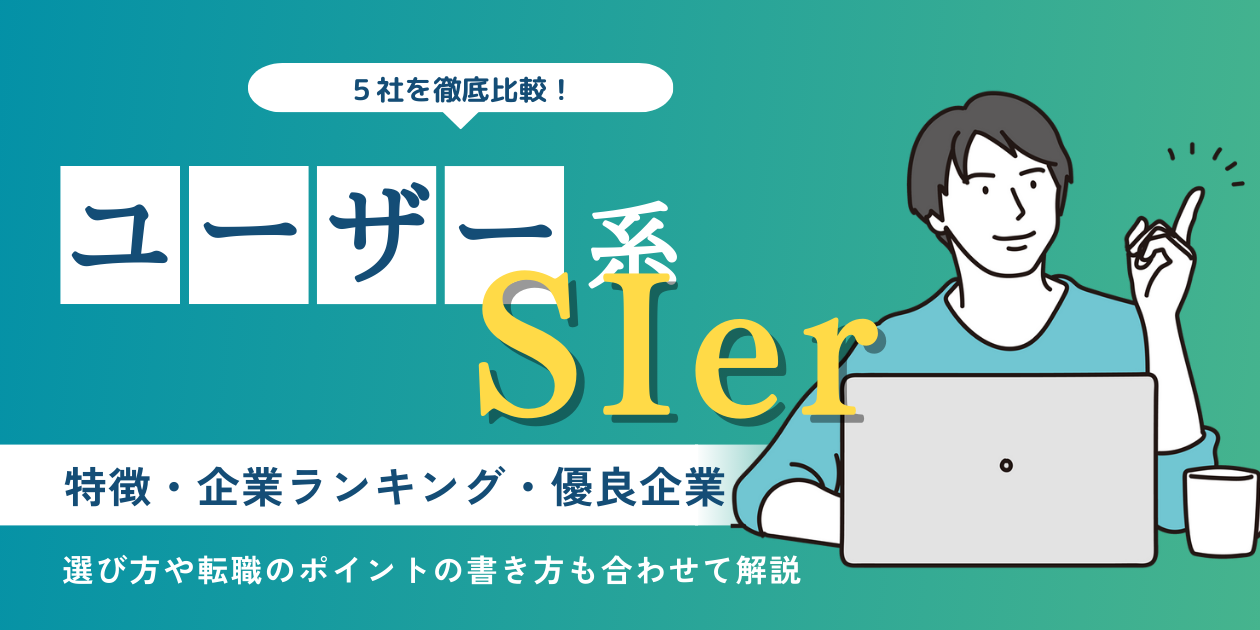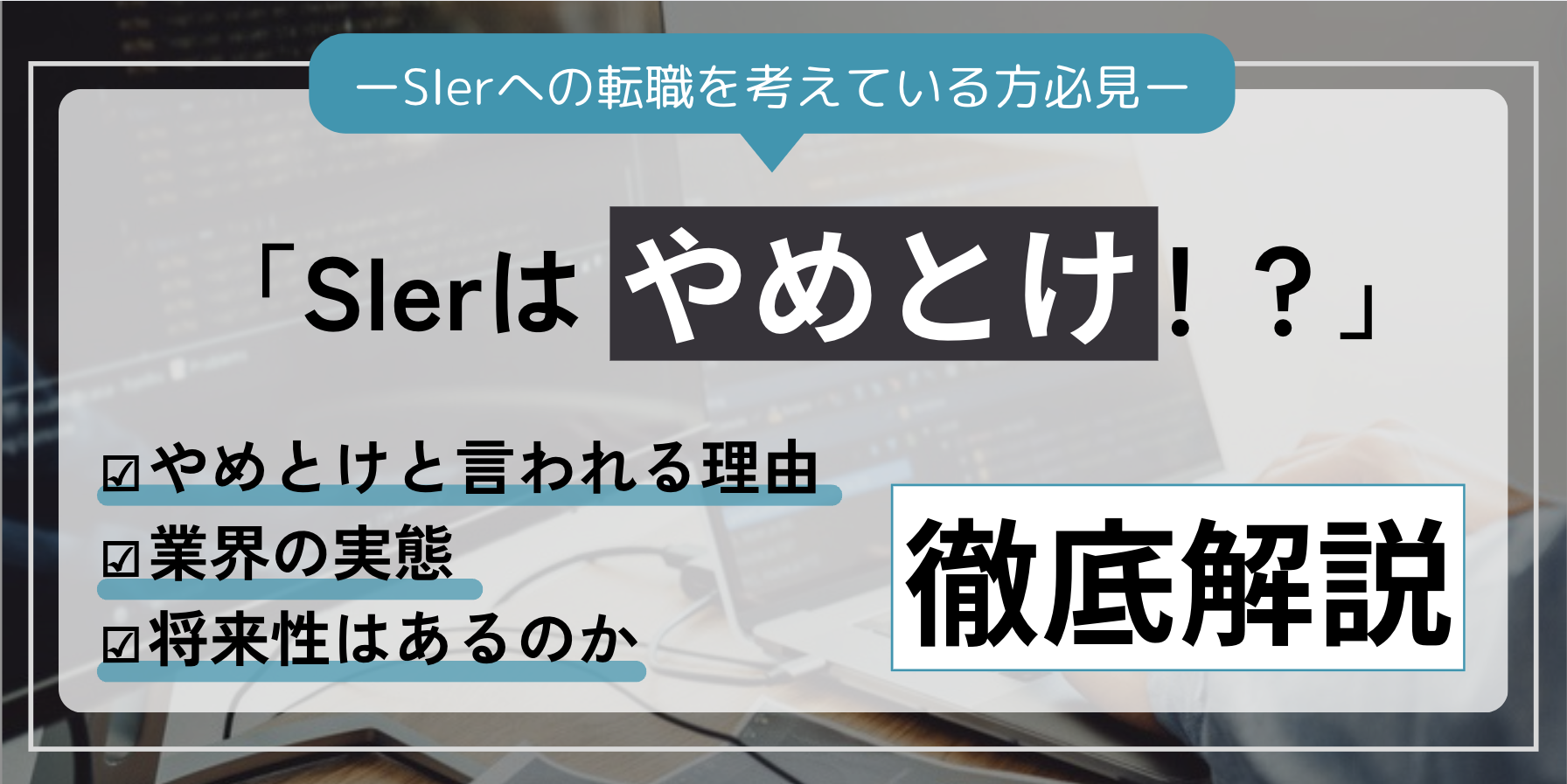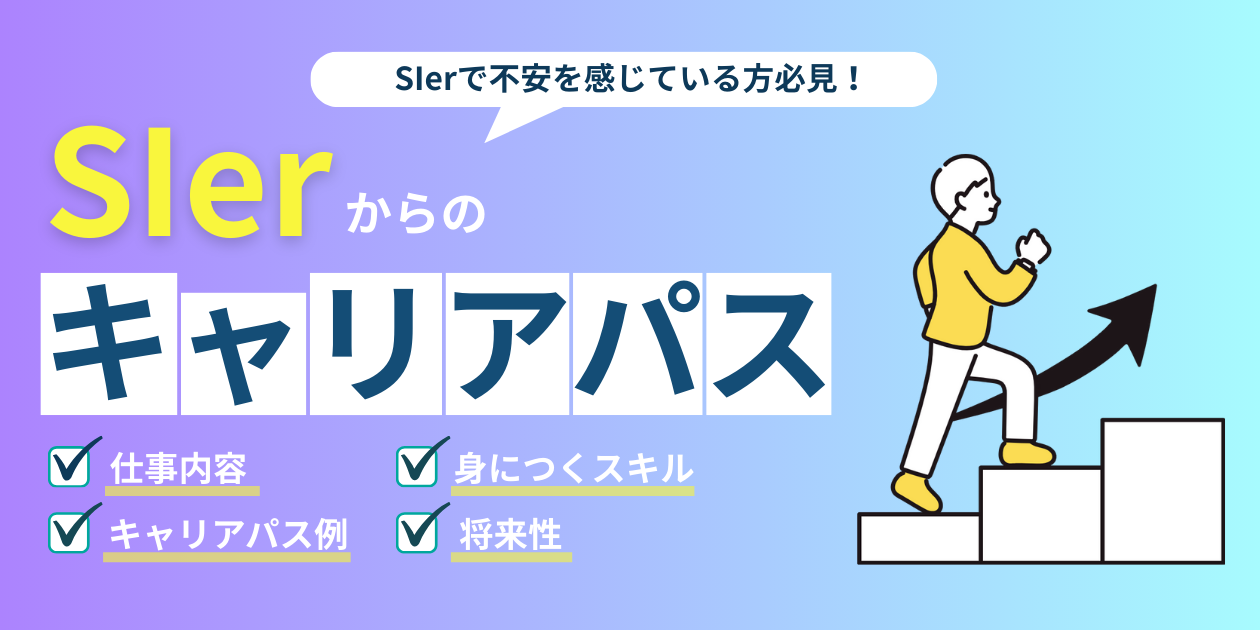SIerとSEの違いは?仕事内容や定義、特徴をわかりやすく解説
「SIerとSEの違いって何?」
IT業界に関する情報を調べていると、この2つの言葉を目にすることは多いはずです。しかし、似たような文脈で使われるため、正確な違いを理解していない人も少なくありません。
本記事では、SIerとSEの定義・仕事内容・種類・必要なスキル・将来性の違いをわかりやすく解説しています。
この記事はPRを含みます
目次
【SIerとSEの違い】それぞれの定義、特徴をわかりやすく紹介
SIer(エスアイヤー)
SIer(エスアイヤー)とは、企業や官公庁などの依頼を受け、情報システムの企画・設計から開発、導入後の運用・保守までを一括して担う企業を指します。
まず、SIerの役割は、社会に必要な仕組みをIT技術で実現することです。システム開発のみならず、業務課題の整理や改善方法の提案といった、コンサルティング的な要素も含まれるのが大きな特徴です。
さらに、SIerの業務形態は1つではありません。自社だけでシステム開発を完結させる場合もあれば、プロジェクトの一部を協力会社に依頼して進めることもあります。
SIerの種類を確認する▼
つまり、どのような体制であっても、依頼元の企業に代わり「システムを設計し、動かし、維持する」ことこそが、SIerの根本的な役割といえます。
SE
SEとは、情報システムの設計や開発に携わる技術者を指します。企業という「組織」を意味するSIerに対して、SEは「人」に焦点を当てた呼び方です。
まず、SEの役割は、顧客の要望を整理し、それをシステムに落とし込むことです。プログラマーがコードを書くのに対し、SEはシステムの全体像を設計する設計する立場であることが多いのが特徴です。
さらに、SEはシステム開発の上流工程だけでなく、プロジェクト全体の進行管理や関係者との調整を担うケースもあります。つまり、技術力だけでなく、コミュニケーション力やマネジメント力も求められる職種といえるでしょう。SEに求められるスキルを確認する▼
【SIerとSE】仕事内容の違いは?
SlerとSEの業務内容をそれぞれわかりやすく解説します。
SIerの仕事内容
SIerの仕事は、顧客の依頼に基づいてシステムを企画し、構築から運用・保守までを担うことです。一般的には以下の5つの工程に分けられます。
SIerの仕事内容の5ステップを詳しく見る
まず、最初のステップは「企画」です。顧客の課題や要望をヒアリングし、それを解決するためのシステムの方向性を検討します。
目的やコスト、導入効果を踏まえて計画を立てるため、業務理解と提案力が求められます。
②要件定義
次に、企画で決まった方針を具体化する段階が「要件定義」です。どのような機能を持つシステムにするのか、実現可能性や予算を考慮しながら仕様を決定します。
新規開発に限らず、既存システムを活用して構築するケースもあります。
③設計・開発
次に行うのが「設計・開発」です。要件定義をもとに基本設計や詳細設計を行い、仕様書を作成します。
その後、プログラマーが設計書に従ってプログラミングを行い、システムを実際に形にしていきます。
④テスト
開発が完了したら「テスト」に進みます。システムが要件どおりに動作するか、不具合がないかを確認する工程です。
単体テスト、結合テスト、総合テストといった段階的な検証を行い、品質を確保した上で本番運用に移行します。
⑤運用・保守
最後は、「運用・保守」です。導入したシステムが安定して稼働するよう、監視やトラブル対応を行います。
また、顧客の新しい要望や改善点に対応し、継続的にシステムをアップデートしていくことも重要な役割です。
SEの仕事内容
SE(システムエンジニア)の仕事内容は、顧客の要望を整理し、それをシステムとして実現することです。システム開発は「要件定義」「設計」「開発」「テスト」「運用・保守」の流れで進みます。SEは、その中でも特に要件定義や設計といった上流工程を担当します。
上流工程では、顧客にヒアリングを行い、必要な機能や仕組みを明確にしたうえでシステム設計に落とし込みます。ここでの判断がシステム全体の品質を大きく左右するため、SEの果たす役割は非常に重要です。
一方で、プログラミング作業そのものはプログラマーが担当します。ただし、SEも進捗を管理したり成果物を確認するなどしてその業務に携わります。
さらに、システムが正しく動作するかを確認し、稼働後に発生したトラブルや追加要望に対応するのもSEの仕事の一部です。
【SIerとSEの違い】それぞれの種類を解説
業務内容などにより、SlerとSEには様々な種類があります。それぞれわかりやすく解説します。
SIerの種類
企業の成り立ちや事業内容によって、SIerにはいくつかの種類があります。ここでは、代表的な5種類のSIerを紹介します。
独立系SIer
独立系SIerは、親会社を持たずに独自で事業を展開しているタイプです。まず大きな特徴は、メーカーやベンダーに縛られないことです。そのため、自由にソフトウェアやハードウェアを組み合わせて提案できます。
また、幅広い業界の案件に携われるのも強みです。ただし、営業からシステム運用まで自社で完結させることが多いため、総合的なスキルが求められる傾向があります。
合わせて読みたい記事はこちら
ユーザー系SIer
ユーザー系SIerは、銀行・保険・商社などの大手企業の情報システム部門が独立して設立されたケースが多いです。
まず親会社やグループ企業のシステム開発・運用を中心に担当し、安定した案件を持てるのが特徴です。
一方で、取り組む案件は親会社の事業領域に沿ったものが中心となります。そのため、業界知識や専門性が必要になる場合があります。
合わせて読みたい記事はこちら
メーカー系SIer
メーカー系SIerは、パソコンやサーバー、ネットワーク機器などを扱うハードウェアメーカーから派生したタイプです。
そして、親会社の製品と連動するシステムの構築を得意としています。
さらに、インフラからソフトウェアまで一貫して提案できる点も強みです。ただし、親会社の影響が強く、開発するシステムがハードウェアに依存するケースも少なくありません。
合わせて読みたい記事はこちら
外資系SIer
外資系SIerは、海外の大手IT企業が日本法人を設立して展開するタイプです。まず役割として、海外で開発された最新のソリューションやソフトウェアを日本市場に導入します。
さらに、大規模で国際的なプロジェクトに関われるのが特徴です。一方で、英語力やグローバル感覚が求められるため、外資ならではのスピード感や実力主義の環境を好む人に向いています。
コンサル系SIer
コンサル系SIerは、厳密にはITコンサルティング企業に分類されます。ただし、システム導入にも深く関与するため、SIerの一種として紹介されることがあります。
特徴は、経営課題の把握からIT戦略の策定、そしてシステム開発までを一貫して支援できる点です。
さらに、経営層とのやり取りが多いため、技術力に加えて高い論理的思考力やコミュニケーション力が求められます。
SEの種類
SEの仕事はシステム開発を通じて顧客の課題を解決することです。しかし、SEといっても役割は一つではありません。ここでは代表的な4つの職種を紹介します。
①アプリケーションエンジニア
アプリケーションエンジニアは、業務システムやWebサービスなどの開発を担います。まず顧客の要望を整理し、要件定義から設計・開発・テスト・運用まで幅広く関わるのが特徴です。
次に必要なスキルとして、JavaやPythonなどのプログラミング言語が挙げられます。また、データベースやネットワークの知識も不可欠です。
さらに、開発はチームで進めるため協調性が重要です。つまり、技術力に加えてコミュニケーション力も求められる職種と言えるでしょう。
②ネットワークエンジニア
ネットワークエンジニアは、コンピューターやサーバーをつなぐネットワークの設計・構築・運用を専門とするエンジニアです。
まず、ルーターやスイッチ、ファイアウォールなどの知識が不可欠です。さらに、外部からの攻撃を防ぐためのセキュリティ対策や、近年重要性が高まっているクラウドの知識も求められます。
③セキュリティエンジニア
セキュリティエンジニアは、情報セキュリティに特化したエンジニアです。具体的には、不正アクセスやサイバー攻撃を防ぐためにシステムやネットワークの脆弱性を見つけ、対策を講じます。
近年は情報流出のリスクが増加しているため、需要が高まっている職種の一つです。
④データベースエンジニア
データベースエンジニアは、データベースの設計・構築・運用を専門とします。データベースは企業の情報を扱う「心臓部」とも言える存在です。
そのため、正確な設計や効率的なデータ管理が求められます。また、SQLをはじめとするデータベース言語の知識や、セキュリティ対策の知識も欠かせません。
【SIerとSEの違い】必要なスキル3選
SIerとSEはどちらもシステム開発に関わります。そのため技術力はもちろん、プロジェクトを円滑に進めるための幅広いスキルが必要です。ここでは代表的な3つを紹介します。
①論理的思考力
まず必要なのが論理的思考力です。顧客の課題を整理し、解決策を筋道立てて導き出す力を指します。システム提案の場面では根拠を持って説明する必要があり、プロジェクトを成功に導くための基盤となります。
②技術的スキル
次に欠かせないのが技術的スキルです。SEは要件定義や設計を行います。そのため、プログラミングの基礎知識やシステム全体の理解が不可欠です。
また、SIerも最新のIT技術やトレンドを把握し、最適なシステムを提案する力が求められます。
③コミュニケーション能力
最後に重要なのがコミュニケーション能力です。顧客とのヒアリングやメンバー同士の調整は日常的に発生します。意思疎通をスムーズに行えることで、課題解決や進行管理が円滑に進みます。
SIerとSEに将来性の違いはある?
結論から言うと、どちらにも将来性はあります。ただし、それぞれが活躍できる領域や求められるスキルには違いがあります。以下で詳しく解説していきます。
SIerの将来性
SIerには将来性があるものの、いくつかの課題も指摘されています。たとえば、クラウドサービスの普及や高コスト体質への批判から「SIerは不要になるのでは」と言われることがあります。
合わせて読みたい記事はこちら
さらに、多重下請け構造によって下流工程の企業ほど労働環境が厳しくなる点も問題視されています。
とはいえ、大規模システムの多くはクラウド化が難しく、特に企業や官公庁の基幹システムでは今後もSIerの存在が欠かせません。つまり、課題への対応を進めつつ役割を進化させれば、SIerは引き続き社会に必要とされるでしょう。
合わせて読みたい記事はこちら
SEの将来性
SEについても、今後の需要が見込まれています。特に要件定義や設計といった上流工程は自動化が難しく、人間の判断力や調整力が求められるからです。
一方で、AIの進化によってプログラミングの一部はすでに自動化が進んでいます。そのため、単純な作業に依存するエンジニアは仕事が減るリスクがあります。
しかし、すべての業務がAIに置き換えられるわけではありません。むしろ、AI・ビッグデータ・クラウド・IoTといった先端分野に関わるSEは将来性が高まります。つまり、変化に対応しながらスキルを磨けるSEは、今後も長く活躍できるといえるでしょう。
SIerとSEの違いを理解してキャリアの選択肢を広げよう
SIerは「企業」、SEは「人(職種)」を指し、それぞれ役割や求められるスキルに違いがあります。どちらにも将来性はありますが、活躍の場やキャリアパスは大きく異なります。
自分に合った働き方を見極めるには、まず違いを理解することが大切です。現在のキャリアについて、「このままで良いのか」と少しでもお悩みの場合は、転職エージェントへの相談がおすすめです。
SIerにおすすめの転職エージェント / サイト
合わせて読みたい記事はこちら
SIerとSEの違いに関するよくある質問
SI業界とSIerは同じものではありません。SI業界は「システムインテグレーションを行う業界全体」を指し、SIerはその業界に属する「システムインテグレーションを手がける企業」を意味します。
SIerが「やめとけ」と言われる理由の一つに、残業時間の多さが挙げられます。
SIerが「やめとけ」と言われる理由を確認する▶︎